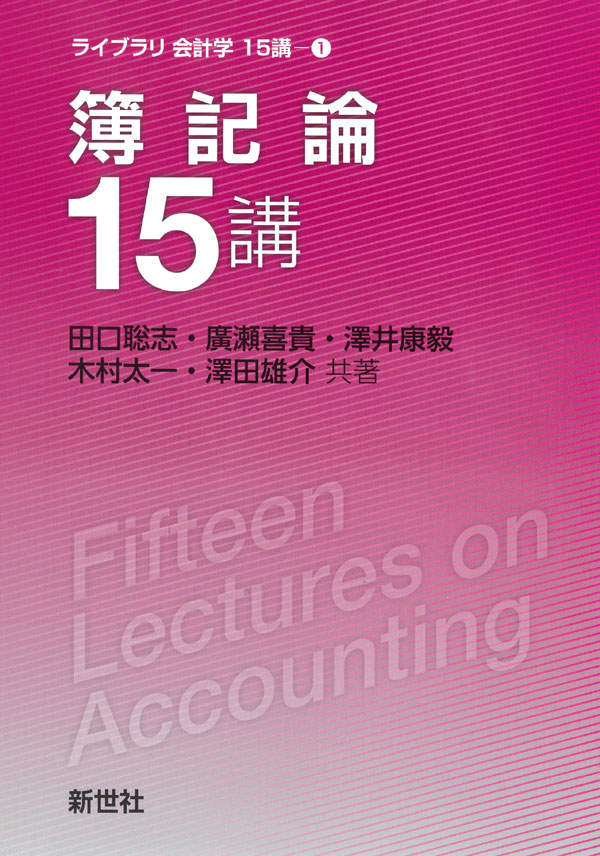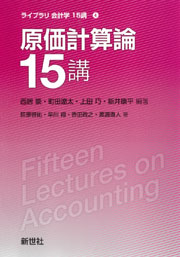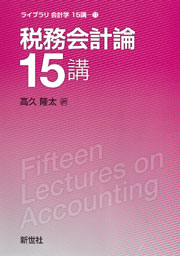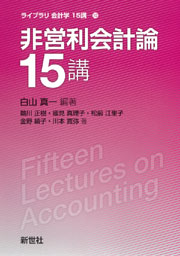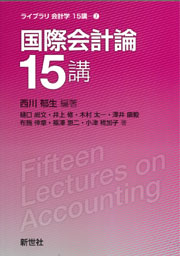第0部 複式簿記の世界へのいざない
第1講 複式簿記の世界へのいざない(1):座談会 Part 1
1. 簿記の第一印象:簿記といつ,どのように出会い,どう思ったか?
2. テキストの見どころ・味わってほしいところ
第2講 複式簿記の世界へのいざない(2):複式簿記の全体像
2.1 会計の意義と財務諸表の必要性
2.2 主要な財務諸表の構造
2.3 基本的な会計用語
2.4 簿記一巡の流れ
2.5 個別の経済事象に対するルール・考え方
練習問題
第1部 複式簿記の「宇宙」:全体を俯瞰する
第3講 記録
3.1 文字や数字の歴史的な萌芽
3.2 記録のコスト・ベネフィットを巡って
3.3 数的記録のもたらす管理のための役立ち
3.4 数的記録と貨幣的記録
練習問題
第4講 二面性
4.1 勘定式記録法
4.2 勘定による諸財産の管理
4.3 勘定による財政状態の把握
4.4 勘定による経営成績の把握
4.5 試算表における二面性
練習問題
第5講 自動的な損益計算・在高計算:二面性のある社会とない社会
5.1 はじめに
5.2 二面性とB/S・P/Lの関係:ステップ
5.3 計算目的と計算システム
5.4 会計の基本等式:試算表
5.5 減算の加算化:複式簿記への道
5.6 クリーン・サープラス関係:損益計算書と貸借対照表の貸借差額の一致
補論 会計の基本等式
練習問題
第6講 貸借対照表と損益計算書のどちらが重要か?
6.1 はじめに
6.2 「自動的な在高計算と損益計算」とクリーン・サープラス関係:前講の復習
6.3 B/SとP/Lのどちらが重要か?:定義の問題
6.4 あえてどちらかを重視したらどうなるか:資産負債観と収益費用観
6.5 例外:試算表等式の関係性が崩れるような定義の拡張
補論 リサイクリングの仕訳と包括利益計算書
練習問題
第7講 会計公準と期間損益計算
7.1 会計学の議論の中心であった会計公準
7.2 複式簿記とエンティティーの公準
7.3 貨幣的評価の公準
7.4 期間損益計算:継続企業の公準と発生主義会計
練習問題
第8講 簿記(学)と会計(学)の関係
8.1 簿記固有の論理
8.2 受託責任機能と簿記
8.3 受託責任機能に固有の記録
練習問題
補講1 座談会 Part 2:簿記(学)と会計(学)の関係を巡って
1. 簿記(学)と会計(学)の関係
2. 形式と内容,それとも
第2部 複式簿記の「地球」:具体的な経済事象への接近
第9講 収益認識:商品販売1
9.1 販売取引の種々の記帳方法
9.2 収益の実現
9.3 収益の認識に関する会計基準の考え方:権利と義務で考える収益認識
練習問題
第10講 棚卸資産:商品販売2
10.1 売上原価の把握
10.2 棚卸減耗と商品評価損
10.3 トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価
練習問題
第11講 設備資産
11.1 減価償却
11.2 減損会計
練習問題
第12講 金融資産
12.1 はじめに
12.2 事業資産と金融資産の違い
12.3 金融資産の仕訳の基本
12.4 有価証券の測定:保有目的
12.5 償却原価法:割引現在価値
練習問題
第13講 負債
13.1 負債の位置づけ
13.2 社債
13.3 引当金
13.4 資産除去債務
練習問題
第14講 資本
14.1 資本の定義
14.2 資本取引と損益取引の区別
14.3 剰余金の配当と分配可能額
14.4 自己株式
14.5 新株予約権
14.6 株式引受権
練習問題
第15講 貸方区分:負債と資本との線引き
15.1 貸方区分問題
15.2 均衡思考体系と非均衡思考体系
15.3 利益計算と貸借対照表貸方区分との関係
15.4 会計主体論
15.5 複式簿記の立場から見た負債と資本との区分の議論
練習問題
補講2 企業組織再編
補.1 企業の組織再編と会計
補.2 企業結合の会計帳簿上の位置づけ
補.3 連結会計の基本構造:個別財務諸表の合算と連結修正仕訳
補.4 企業結合(合併)の会計処理
補.5 連結会計の基本:連結修正仕訳
練習問題
補講3 座談会 Part 3:次なる学習,そして研究へ向けて
1. 本書執筆者の研究について
2. 会計研究の様々なアプローチ
3. 会計は実験できる:仕組みと人間心理の相互作用に迫る
4. 読者が次に学習・研究すべき道はどこか
5. 「古典」や歴史を紐解く重要性
あとがき
読書案内
謝辞
参考文献一覧
索引
第1講 複式簿記の世界へのいざない(1):座談会 Part 1
1. 簿記の第一印象:簿記といつ,どのように出会い,どう思ったか?
2. テキストの見どころ・味わってほしいところ
第2講 複式簿記の世界へのいざない(2):複式簿記の全体像
2.1 会計の意義と財務諸表の必要性
2.2 主要な財務諸表の構造
2.3 基本的な会計用語
2.4 簿記一巡の流れ
2.5 個別の経済事象に対するルール・考え方
練習問題
第1部 複式簿記の「宇宙」:全体を俯瞰する
第3講 記録
3.1 文字や数字の歴史的な萌芽
3.2 記録のコスト・ベネフィットを巡って
3.3 数的記録のもたらす管理のための役立ち
3.4 数的記録と貨幣的記録
練習問題
第4講 二面性
4.1 勘定式記録法
4.2 勘定による諸財産の管理
4.3 勘定による財政状態の把握
4.4 勘定による経営成績の把握
4.5 試算表における二面性
練習問題
第5講 自動的な損益計算・在高計算:二面性のある社会とない社会
5.1 はじめに
5.2 二面性とB/S・P/Lの関係:ステップ
5.3 計算目的と計算システム
5.4 会計の基本等式:試算表
5.5 減算の加算化:複式簿記への道
5.6 クリーン・サープラス関係:損益計算書と貸借対照表の貸借差額の一致
補論 会計の基本等式
練習問題
第6講 貸借対照表と損益計算書のどちらが重要か?
6.1 はじめに
6.2 「自動的な在高計算と損益計算」とクリーン・サープラス関係:前講の復習
6.3 B/SとP/Lのどちらが重要か?:定義の問題
6.4 あえてどちらかを重視したらどうなるか:資産負債観と収益費用観
6.5 例外:試算表等式の関係性が崩れるような定義の拡張
補論 リサイクリングの仕訳と包括利益計算書
練習問題
第7講 会計公準と期間損益計算
7.1 会計学の議論の中心であった会計公準
7.2 複式簿記とエンティティーの公準
7.3 貨幣的評価の公準
7.4 期間損益計算:継続企業の公準と発生主義会計
練習問題
第8講 簿記(学)と会計(学)の関係
8.1 簿記固有の論理
8.2 受託責任機能と簿記
8.3 受託責任機能に固有の記録
練習問題
補講1 座談会 Part 2:簿記(学)と会計(学)の関係を巡って
1. 簿記(学)と会計(学)の関係
2. 形式と内容,それとも
第2部 複式簿記の「地球」:具体的な経済事象への接近
第9講 収益認識:商品販売1
9.1 販売取引の種々の記帳方法
9.2 収益の実現
9.3 収益の認識に関する会計基準の考え方:権利と義務で考える収益認識
練習問題
第10講 棚卸資産:商品販売2
10.1 売上原価の把握
10.2 棚卸減耗と商品評価損
10.3 トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価
練習問題
第11講 設備資産
11.1 減価償却
11.2 減損会計
練習問題
第12講 金融資産
12.1 はじめに
12.2 事業資産と金融資産の違い
12.3 金融資産の仕訳の基本
12.4 有価証券の測定:保有目的
12.5 償却原価法:割引現在価値
練習問題
第13講 負債
13.1 負債の位置づけ
13.2 社債
13.3 引当金
13.4 資産除去債務
練習問題
第14講 資本
14.1 資本の定義
14.2 資本取引と損益取引の区別
14.3 剰余金の配当と分配可能額
14.4 自己株式
14.5 新株予約権
14.6 株式引受権
練習問題
第15講 貸方区分:負債と資本との線引き
15.1 貸方区分問題
15.2 均衡思考体系と非均衡思考体系
15.3 利益計算と貸借対照表貸方区分との関係
15.4 会計主体論
15.5 複式簿記の立場から見た負債と資本との区分の議論
練習問題
補講2 企業組織再編
補.1 企業の組織再編と会計
補.2 企業結合の会計帳簿上の位置づけ
補.3 連結会計の基本構造:個別財務諸表の合算と連結修正仕訳
補.4 企業結合(合併)の会計処理
補.5 連結会計の基本:連結修正仕訳
練習問題
補講3 座談会 Part 3:次なる学習,そして研究へ向けて
1. 本書執筆者の研究について
2. 会計研究の様々なアプローチ
3. 会計は実験できる:仕組みと人間心理の相互作用に迫る
4. 読者が次に学習・研究すべき道はどこか
5. 「古典」や歴史を紐解く重要性
あとがき
読書案内
謝辞
参考文献一覧
索引